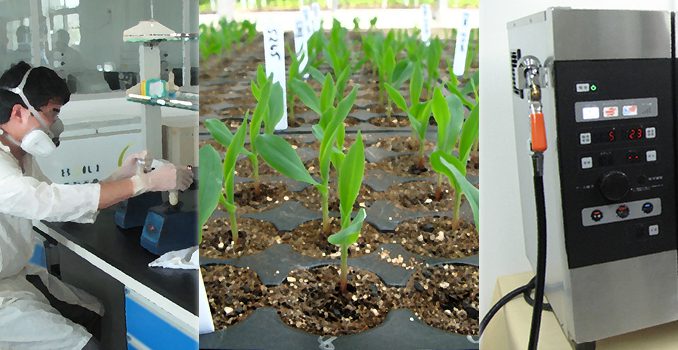
3月22日、食の信頼向上をめざす会が「メディアとの情報交換会」を開催。今回は「東北地方太平洋沖地震と風評被害の防止に向けて」と題して、東京工業大学原子炉工学研究所所長の有冨正憲氏と、秋田大学名誉教授で医学博士の滝澤行雄氏の両氏を招いて講演を行った。滝澤氏は、専門の公衆衛生・環境保健の立場とこれまでの放射線に関する事象に対する取り組みの経験から、放射能の影響と対応について説明した。
《滝澤行雄氏の講演の骨子》
放射能汚染の来歴
最初に過去の放射能汚染を振りかえる。
人工放射能による汚染は、米国での人類史上初の核爆発実験に始まり、広島、長崎への原子爆弾投下、ビキニ環礁の水爆実験、各国によるたび重なる核実験と続いてきた。
世界初の原子炉重大事故は、1957年に英国ウインズケール(現セラフィールド)の再処理施設で発生した火災事故だ。
このときに多量の放射性物質が外部に放出された。そして、25歳以下の若い人たちに白血病、リンパ腫の発症率が高いのではないかと報告された。しかし、その後各国の放射線専門家が検討したが、現在ははっきりした影響はないという結論になっている。
そして1986年、旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所事故が発生した。ここでとくに問題となった放射性同位体が、半減期が約30年のセシウム-137や28.8年のストロンチウム-90などだ。もしセシウム-137の放出がなければ、事故による影響は1年を待たずに収束しただろう。
事故以降のセシウム-137の体内摂取量は約1年後に男性1200Bq(ベクレル)、女性800Bqと最大値に達した。しかし3年後には無視できる程度に減少した。
避難の有効性については、このときのデータから考えると、発生源から半径30㎞離れるというのが一つの物差しになると言える。
また、放射性雲の中に放射能があるので、この雲の移動を考えながら避難することが重要だ。
降雨、降雪による放射能沈着も問題になる。地表に沈着した放射性物質が被曝源として最も長期かつ多い。降水がもたらす湿った沈着物(wet deposition)は、粉塵のようなもの(dry deposition)より1桁以上多い。これに気象条件、放射性雲の濃度などの要因が加わると2桁以上多いことがある。
地表に沈着した放射性物質による被曝は、これらが出すγ線を直接受けるものと、これに汚染された飲食物の摂取によるものとがある。
緊急時の防護対策
放射性降下物は、歴史的にはまず大気圏内核実験で問題になった。中でも巨大粒子は死の灰と呼ぶようになった。
たとえば中国のたび重なる核実験の結果、日本でも何度も放射性降下物が観測された。私が新潟大学にいた頃は、10月の国慶節の頃から12月にかけて多く観測された。中国の核実験で発生した死の灰は、ジェット気流に乗って2~3日で到達する。これを観測して内閣対策本部に報告していた。とくに濃度が高いときには雨に濡れないようにといった助言を伝えたものだ。
日本の緊急時における防護対策には、「原子力発電所周辺の防災対策について」(1980年)、「緊急時環境放射線モニタリング指針」(1984年)というものがある。これらでは、事象発生後の対処を初期、中期、復旧期と分けて決めている。中期に屋内退避、避難を行い、これが済む頃に飲食物の摂取制限を出そうということになっている。
飲食物の摂取については、チェルノブイリ原子力発電所事故を受けて、1986年10月に厚生省(現厚生労働省)がECの基準などを参考に暫定基準を定めた。ヨウ素-131については、牛乳220Bq/l、野菜7400Bq/kg、セシウム-134とセシウム-137については、全食品について370Bq/kgなどを定めている。
なお、これら食品の摂取制限の基準は、国によって異なる。それは、食品の摂取スタイルが国によって異なるためだ。ヨーロッパではとくに乳製品と肉を問題にしており、日本では野菜を問題にしている。
そして今回、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、3月17日に食品安全委員会が暫定値を出した(「東北地方太平洋沖地震の原子力発電所への影響と食品の安全性について」3月17日。以降更新中)。飲料水、牛乳・乳製品で300Bq/kg、野菜類(根菜、芋類を除く)で2000Bq/kgなどで、野菜類は従来7000Bq/kgとしていたが、1/3以下の厳しい基準を設けている。
放射性核種の移行と人体への影響
さて、放射性核種はどのように陸上での移行経路をとり、人体に線量を与えているか。
大気中の汚染は、まず外部被曝として人体に影響する。とくに、直接土に接する農家は外部被曝を多く受ける。陸上の核種は長い期間をかけて減衰するから、汚染地域に住んでいる人々には外部被曝として長期間影響してくる。
また、それから放射性降下物が土壌に入り、そこで栽培した農作物を食べることで地域外の人々の体内に入る。
地球規模の放射性降下物の研究では、ストロンチウム-90とセシウム-137の総沈着量の約90%は、湿性沈着すなわち降水によるとわかっている。したがって、雨にはできるだけ濡れないようにすることが重要である。
事故後最初の期間は、植物の表面沈着が支配的だが、長期間においては、植物の根からも吸収される。
また、土壌の中でも粘土および有機物にセシウム-137が蓄積しやすい。土壌汚染はpHなども影響する。
動物については、食物連鎖によって核種が濃縮される。
人間への主要な経路としては、ストロンチウム-90、ヨウ素-131、セシウム-137は、牛乳の摂取によるものが多い。またプルトニウム-239、プルトニウム-240は甲殻類、ポロニウム-210は魚などの海産物に蓄積しやすい。
ビキニ環礁での水爆実験の後、当初焼津港に水揚げされたマグロ類が受けていた汚染は放射性降下物が体表面に付着した表面汚染であった。その後体内汚染が増えている。魚介や藻類は、海水から元素を選択的に取り込む傾向が著しく、生体成分として蓄積する。
農作物については、表面汚染と体内汚染とがある。体内汚染は根からだけでなく、茎葉に付着したものを吸収するものもあり、植物体内の他の部位に転流して蓄積する。
食物を通じて人体に移行する放射性物質の移行量を評価する際は、まず対象地域住民の平均的食品摂取量を求める。その上で、ALARA(As low As Reasonably Achievable。合理的に達成可能なだけ低く/放射線防護の最適化)の考え方をとる。地域特性を考慮しながら、きめ細かい基準を出すことだ。
日常生活での被曝
人は平時でも自然界からの被曝を受けている。これにも外部被曝と内部被曝がある。
日常生活での外部被曝源には、土壌や岩石に含まれる放射性物質からの大地放射線と宇宙放射線とがある。地球の磁場を通り抜けた宇宙線は大気中の窒素や酸素と衝突して消滅するが、その際に中性子、ミュー粒子、パイ粒子、トリチウムなどを生成する。
日常生活で1年間に受ける外部線量(平均)は、大地放射線が世界で0.48mSv(ミリシーベルト)、日本で0.38mSv、宇宙放射線が世界で0.39mSv、日本で0.29mSvとなっている。
日常生活での内部被曝は飲食物による。各食品群ごとの実効線量は、たとえば穀類、芋類、砂糖類、豆類などは0.022mSv、野菜類、果物類、きのこ類などは0.010mSv、肉類は0.0029mSv、魚類・貝類は0.64mSvとなっている。魚介類の線量が比較的多い。
食品から放射能を除去する方法はある。
キュウリ、ナスなどの果菜類では、水洗いすることでストロンチウム-90の50~60%が除去される。ホウレンソウ、シュンギクなどの葉菜類では、煮沸処理(あく抜き)をすることで、セシウム-137、ヨウ素-131、ルテニウム-106といったものが50~80%除去される。またキュウリなどは酢漬けにすることで放射性降下物の90%が除去される。
牛乳のストロンチウム-90、セシウム-137、ヨウ素-131は脱脂粉乳に移り、精製したバターへの移行は1~4%となる。
食肉中のセシウム-137は、食塩水と硝酸カリを含む水溶液に1週間浸しておくと徐々に減っていき、最終的には初期濃度の約5%まで減少する。また、予め肉を凍結しておいて、解凍後4~5時間10%食塩水処理するだけで90~95%のセシウム-137を除去することができる。
飲料水中のヨウ素-123は、フェロシアン化鉄イオン交換樹脂を使って100%除去することができるなどの方法が確立されている。
被曝線量の限度
ICRP(国際放射線防護委員会)は、一般公衆が1年間にさらされてよい人工放射線の限度として1mSvを勧告している。また、1000mSvの被曝でガン死亡率が5%増加するとしている。
ところで、ブラジルのガラバリ海岸の一部では、大地からγ線で175mSv、市街地でも8~15mSvの自然放射線がある。また、インドのケララ州では平均3.8mSv。ここの住民では他の地域と比較しても人体に悪い影響は見られない。
これらから考えて、0.1~30mSvの範囲は通常生活の範囲内と見て、安心レベルと見ていいのではないかと考える。
人工放射線の身近なものには医療で用いるものがある。X線健診やCTスキャンなど、自然放射線にくらべるとたいへん高い値を示すが、今のところ健康影響は報告されていない。
しかし、やはり自然からの被曝よりも高ければ、リスクが高まるかもしれない。そこで30mSvから500mSvまでを注意レベルとしている。
500mSv以上では、急性障害、慢性障害など、いろいろな種類の臨床兆候が現れてくる。これは危険レベルと考える。
JCO事故では、深刻な被曝を受けた3人のうち、16000~20000mSvの被曝を受けた人と、6000~10000mSvの被曝を受けた人が亡くなった。一方、1000~4500mSvの人は助かった。
これから考えると、5000mSv以上の放射線を受けると死亡する危険が急増すると考えられる。
心理的放射能ショック
ポーランドではチェルノブイリ原子力発電所事故の2日後に通常の約50万倍の強い放射能を各地で検出し、これによるパニックが起こり、政府は苦慮した。心理的な放射能ショックと言える。
このとき、国連科学委員会の委員長経験のあるヤオロウスキー博士が甲状腺腫瘍の予防として安定ヨウ素剤を使うように進言し、政府はこれを1850万人に配布した。
しかし同博士は後にこれを再評価して、安定ヨウ素剤の予防内服は無意味であったと反省している。安定ヨウ素剤の予防内服をしなかった人たちの甲状腺被曝線量は約50mSvであり、このレベルの放射線を照射しても甲状腺ガンの誘発率はゼロであることが医学的研究で明らかになったのが理由だ。
チェルノブイリ原子力発電所事故のときに、スウェーデン国立放射線防護研究所(SSI)が出した対策基準はこのようなものであった。すなわち、窓の開閉は差し支えない。安定ヨウ素剤の予防内服は必要ない。妊婦への心配はない。母乳を中止しなくてよい。屋根などで集めた雨水を飲んではいけない。水道水や個人の井戸水は飲用してもかまわない。牛乳は規制しない。大気中に数日曝露された牧草は飼料に供さない、などだ。
正しい評価を元に対策を考えることが重要だ。
※記事は当日の発表を記者がまとめたもので、文責はFoodWatchJapan編集部にあります。東北関東大震災による影響、とくに福島第一原子力発電所に関する事態は刻々と変化しており、この記事の内容と異なる事柄も起こり得ます。最新の情報に注意してください。



