
恢復するチェーン
「someday――いつか」という日は来ない(4)
(7)前向きの危機感 閉塞感に満ちているからこそ、今は何事につけ前向きに取り組むべきだ。しかし、会社の規模を問わず企業の正規社員である人々を見ていると、「そんな社会と私は関係ない」と考えているように見えることが多い。変化せず、むしろ変化を求めない人の方が多数であるように感じるのである。 そういう人でも、いろいろな情報を取り、よく学んでいるのである。学びにかけては、零細企業とくに凋落の過程にある […]











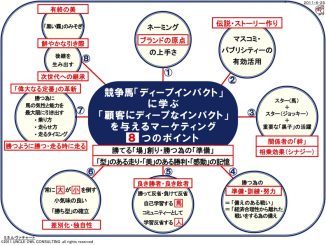
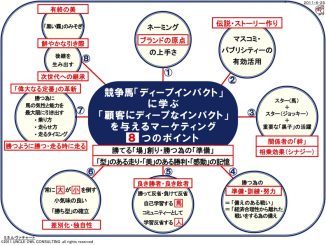
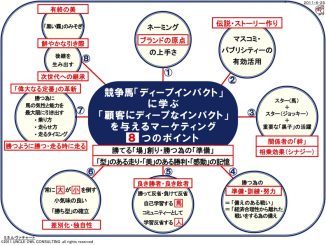
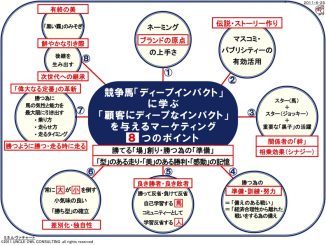
Copyright © Kosetsusha, Inc. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.