
洋酒文化の歴史的考察
VIII 日本人の知らないジャパニーズ・カクテル/ミカド(17)
出来上がったジャパニーズ・カクテルの色は、やや赤みが強かった。アンゴスチュラ・ビタースではなく、オリジナルどおりにボガーツがあればと思う。生産中止となったそれを再現する方法は伝わっているが、それを試そうと思えない事情がある。



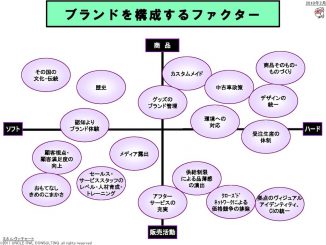





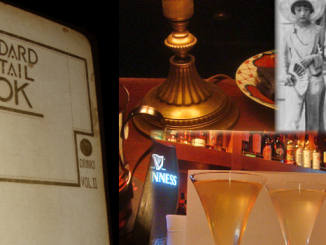


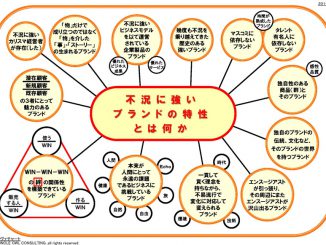


Copyright © Kosetsusha, Inc. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.