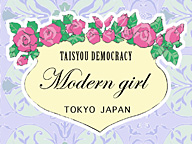日本に洋酒文化が定着していったプロセスを追う本シリーズ。その手がかりとして最初にスポットを当てたのが、大正期から現れたモダン・ガールたちだ。さて、尾竹紅吉に「五色の酒」を差し出した奥田駒蔵だが、彼がそれを調製した事情を考えると次々に不思議な点が出てくる。
桃色の酒、青い酒
「靑いお酒」は日本には存在しないから、これが彼女の指す洋酒に含まれることは、まず間違いない。そして、ここで言う「洋酒の一、二種」は「靑いお酒」と同列ではない。つまり、文頭の「桃色のお酒」も含めて厳密には重複表現ながら「洋酒の一、二種」=「桃色のお酒」「靑いお酒」ということになる。
では、「桃色のお酒」とは何なのか。
戦前流通していた桃色の洋酒にはクレーム・ド・ローズとクレーム・ド・ヴァニーユ(バニラ)がある。普及の度合いからすると元治元(1864)年の輸入リストと共通するバニラにいささかの分があるが、もし尾竹が舶来洋酒を取り揃えていた亀屋鶴五郎商店で「何か洋酒を」と尋ねたとしたら薔薇の酒により心を惹かれそうだ。
次に「靑いお酒」の正体に迫ろう。少し時代は後になるが、大正5年に村井銀行地下のフランス料理店「東洋軒」オーナーが新聞記者から尋ねられた際、彼は青い酒の種類としてアブサン/ブルーキュラソー/アンゼリカ/ペパーミントを挙げている。
アブサンに関しては度数が高く(日本に入ってきていた最もメジャーなペルノーSA社製で68度ある)原産国であるスイスやフランスでもストレートで飲むつわものは滅多にいなかった。
ブルーキュラソーは、今でこそ「青い珊瑚礁」や「チャイナ・ブルー」「ブルー・ハワイ」に使われる青い酒の代表格だが、戦前に日本での輸入実績はあるものの認知度が低かった。当時「ブルー」と表記するカクテルでも紫色のパルフェ・タムール(スミレのリキュール)を使っていたし、戦前のキュラソーは褐色が一般的だったから、こちらもまずないだろう。
アンゼリカ(セイヨウトウキ)は現在もなお高級リキュールの代名詞であるシャルトリューズにも使われているが、これが単体で使われているリキュールは寡聞にして知らない。現在日本でも入手可能なリキュール・ド・サパン(モミの木のリキュール)に近い香りと推察されるが、これも明治末期に入っていた事実が確認できない。
難物揃いの青い酒
ここでいささか脱線すると、筆者は以前サパンをバーに持参してバーテンダーの方に色々調製していただいたことがある。色は淡い緑で、香りは悪くないのだが、カクテルにすると作り物っぽくなって甘さが暴れることに難渋した記憶がある。
今考えるとタンブラーに数滴入れて氷と共にステアし、完璧に水を切って香りだけを残したグラスに氷を注ぎ足してジン・トニックを作ってもらえばうまかったかもしれない。

この手法は「リンス」という。味に甘みを加えず、香りだけを残す、通常はカクテルグラスやロックグラスで行う便法だが、バーボン・ウイスキーにノチェロ(クルミのリキュール)を加えたり、ラム酒にマリブ(ココナッツのリキュール)を加えたりする手を筆者はよく使うので、興味のある方は知り合いのバーテンダーに頼んでみるといいかもしれない。
もう一つ脱線すると、青い酒は意外な国にある。「竹葉青」という酒で、今から20年以上前、名前だけを知っていた筆者が新橋の中華料理屋で見かけて試したことがある。中国の方には怒られそうだが、ベトナムの「ネップ・モイ」、タイの「メコン」と並んで筆者には数少ない苦手な味の部類になる。
閑話休題、ここは戦前「靑い酒」の代名詞であったペパーミント、それも自分の絵が100円という高額で売れた彼女がお祝いに使うのだから、明治5年以来ミント・リキュールの代表格だったジェット「ピペルミント」だと考えて、ほぼ間違いないだろう。
付言すると、尾竹の言う「日本の黄色い酒」で筆者がすぐに思いついたのは梅酒だが、これに関しては専門外でもあるので憶測の域を出ないことをご承知いただきたい。
フレンチの料理人がカクテルを調製した謎
さて、洋酒を口にした経験のある尾竹にとっても、小さなグラスの中で五色に分かれたカクテルは衝撃であったからこそ、すぐに「五色の酒」を「青鞜」で取り上げたことは容易に察しが付くが、ここで一つの疑問が湧いてくる。
「メイゾン鴻之巣」主人の奥田駒蔵は川魚料理出身の板前で、ベルギーでフランス料理の経験は積んだものの、バーテンダーではない。その彼がどうして5色に注ぎ分けたプース・カフェの存在と製法を知ったのだろう。
現在ではプース・カフェと言えば3色から7色の色に分かれた、細長いグラスに入ったカクテルの代名詞なのだが、本来の意味は「食後酒全般」、つまりメインとなる料理を終え、コーヒーの後に飲むもの……といった意味であり、昔はメインが終わってコーヒーを飲んだ後でシガーをくゆらしながら傾けるブランデーも「プース・カフェ」と言われていた。
さらに言えば、世界最古のJ.トーマスのカクテルブック※ではグラスの中で色分けしたカクテルを「プース・ラムール」と表記しており、一方Santina’s Pousse
Café(コニャック/マラスキーノ/キュラソー等量)の説明では「よく攪拌する」とわざわざ注記まで付けている。
このことはフランス料理という奥田の畑を考えるとさらに厄介で、フランスでは長くカクテルは「新世界(米国)で始まった氷とかき混ぜて作る野蛮な飲み物」として、ワインやコニャックに比して一段も二段も下に見られていた。
つまり奥田が本格フランス料理を志向した場合、邪道であるカクテルを学ぶ機会が任地ベルギーであったとは思えない。彼はどうやってカクテルの製法を知ったのだろう?
※「The Bartender’s Guide / How to Mix Drinks / THE Bon Vivant’s Companion」(Jerry Thomas/1862)*復刻版(洋書)あり→こちら
(画・藤原カムイ)