
食品安全情報(化学物質)
エナジードリンクのリスクは
国立医薬品食品衛生研究所は、食品安全情報(化学物質)No.12(2012.06.13)を発表した。フランス食品・環境・労働衛生安全庁(ANSES)はエナジードリンクのリスクについて厳密な調査を行っている。欧州食品安全機関(EFSA)は、食品中のパーフルオロアルキル化合物について評価を行い、食事からの暴露が低いことを報告している。カナダHarper政権は、食品安全への政府機能を強化する法案を提出した […]











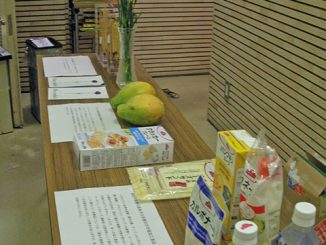



Copyright © Kosetsusha, Inc. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.