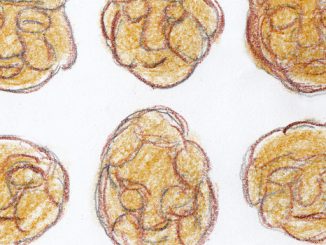今年の第93回アカデミー賞は、コロナ禍の影響で通常より2カ月遅れとなる4月25日(現地時間)に授賞式が予定されており、先日そのノミネートが発表になった。
昨年、韓国映画「パラサイト 半地下の家族」(本連載第225回参照)が、アカデミー賞史上初となる非英語での作品賞受賞をはじめ監督賞、脚本賞、国際長編映画賞の計4部門で受賞したのは記憶に新しいが、今年も韓国系アメリカ人のリー・アイザック・チョン監督による「ミナリ」が、作品賞、監督賞、主演男優賞、助演女優賞、脚本賞、作曲賞の計六部門にノミネートされ、注目されている。そこで今回は、アーカンソー州の片田舎で新規就農した韓国系移民の家族を、監督の幼少期の体験をもとに描いたこの作品について述べていこうと思う。
夢の実現を支えたヒヨコ鑑別
韓国からアメリカへの移民は、1965年にアメリカの移民法が改正されて移民枠が拡充されたのをきっかけに急増し、本作の舞台である1980年代のレーガン政権時代には毎年3万人を超える人々が移民するようになった(※1)。2018年の韓国系アメリカ人の人口はアメリカの総人口の約0.6%にあたる約190万人。これはアジア系アメリカ人のうち、中国系(約514万人)、インド系(約451万人)、フィリピン系(約401万人)、ベトナム系(約216万人)に次ぐ5番目で、日系(約154万人)より多い数字である(※2)。
本作の主人公、ジェイコブ(スティーヴン・ユァン)は、物語に先立つ10年前、軍事独裁政権下で民主化の遅れていた韓国から妻のモニカ(ハン・イェリ)を連れ、成功を夢見てアメリカに渡ってきたことが彼のセリフからうかがえる。アーカンソーに来る前はカリフォルニアやシアトルで働いていた。根深い人種差別が存在するアメリカ社会の中で働き口を得るために役立ったのが養鶏用ヒヨコの雌雄鑑別技術。この難易度が高い日本生まれの技術(※3)のスキルを持っていたおかげでジェイコブは将来事業を興すための資金を貯めることができた。そしてアーカンソーでもモニカと共に孵卵場で副業として働き、農園が軌道に乗るまでの家計を支えることになる。
アーカンソーの孵卵場で働き始めたジェイコブが休憩時間に息子のデビッド(アラン・キム)と煙突からたちのぼる煙を見上げるシーンがある。あれは何? と尋ねる息子にオスの廃棄だと答える父。廃棄って何? とさらに問うデビッドにジェイコブは殺処分だとは言わず、オスは卵を産まないしおいしくない。役立たずだ。俺たちは人の役に立たなければならないんだと諭す。オスのヒヨコは社会の中で切り捨てられるマイノリティーの象徴であり、俺たちはそうはならないぞという決意表明である。
そしてこのシーンは監督が敬愛する小津安二郎の「小早川家の秋」で、笠智衆演じる農夫が火葬場の煙突の煙を見上げながら小津作品に通底するテーマのようなあるセリフを言うシーンのオマージュになっている。さらにヒヨコの焼却は、ジェイコブ家の庭で繰り返される不用品の野焼きとともに、“火”の伏線となっている。
キムチ好きの“救世主”
毎年増え続ける韓国系アメリカ人にとって、故郷の味は懐かしいはず。ならば韓国料理に使う野菜のニーズがあるのではないか? ジェイコブはそう考え、農業経営に事業ターゲットを定め、ウォルマート発祥の地であるアーカンソー州ロジャーズ郊外の高原地帯に、広大な肥沃な土地を見つけて取得する。前の所有者が手放してから荒れ放題の耕作放棄地には雑草が生い茂っていた。住まいはトレーラーハウス。心臓の病気を抱えたデビッドが心配なモニカは、最寄りの病院まで車で1時間もかかる僻地に越すことに不満を隠さない。しかし農業経営の成功が家族の幸福につながると信じて疑わないジェイコブは、農場の基盤作りに奔走する。
まずは“水”の確保。農業用水などない僻地のため灌漑は地下水に頼らざるを得ない。怪しげなダウジング業者が営業をかけてくるが、似非科学など信用しない合理的思考の持ち主のジェイコブは、森の近くは水源が豊富だと推測し、見事自力で井戸を掘り当てることに成功する。しかし、その後も灌漑には苦労させられることになる。本作では“火”と並んで“水”も夢の実現を阻む壁の象徴となっている。
次は農地の整備。ジェイコブは朝鮮戦争に従軍経験があるという隣人のポール(ウィル・パットン)から中古の小型トラクタを入手し、プラウ(洋式の鋤)で地表の雑草を鋤き込み、下層の土を表面に露出させる反転耕起を行う。
さらにポールを仕事のパートナーとして雇い入れ、白菜、ナス、パプリカ、サンチュ等、韓国野菜の栽培に本格的に取り組み始める。ポールは朝鮮戦争のPTSDなのか、日曜日になるとゴルゴタの丘に向かうイエス・キリストのように十字架を背負って歩いたりする奇行が見立ち、近隣住民から変わり者と呼ばれていた。しかし、彼の農業技術には確かなものがあり、経験の浅いジェイコブのよきサポート役になっていく。
たとえば、マルチ(畑に使う被覆材)を張ってサンチュの苗を植えるのに、間隔を狭めてたくさん植えたがるジェイコブに対し、間隔をたっぷりとって植えるのがアーカンソー流だとアドバイスする。彼はまた、出荷直前にバイヤーからドタキャンの連絡が入って荒れるジェイコブをなだめもする。ジェイコブがポールを家に招いた家族との食事で、モニカが気を利かせてポールの前のキムチを下げようとしたところ、「遠ざけないで。大好きなんだ」と言うシーンは朝鮮戦争の従軍経験あってのことだ。
“おばあちゃんのクッキー”とミナリ
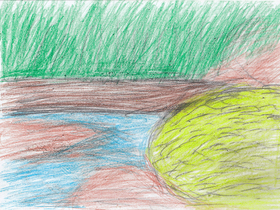
ある出来事がきっかけで夫婦喧嘩になってしまったジェイコブとモニカは話し合い、ソウルに住むモニカの母ソンジャ(ユン・ヨジョン)を呼び寄せてデビッドと姉アン(ノエル・ケイト・チョ)の面倒をみてもらうことにする。ソンジャが持参した韓国みやげの粉唐辛子や煮干しに涙するモニカ。入手困難な故郷の食材を視認しただけで味覚の記憶がよみがえり、涙腺が刺激されるという経験に共感される方もいることだろう。
一方、デビッドにとってのソンジャは、料理しない、お気に入りのマウンテンデューを横取りする、いびきがうるさい、男物のパンツをはく、TVのプロレス中継に夢中、花札のゲーム中に四文字言葉を連発する等々、“クッキーを焼いてくれる理想のおばあちゃん像”とはかけ離れたものだった。日曜礼拝でオネショを暴露されるに至って、デビッドの怒りは爆発。ソンジャにあることを仕掛けるのだが、それをきっかけに仲良くなるという楽しい展開は、おそらく監督の祖母に対するノスタルジアであろう。
そして、作品のタイトルとなったミナリ(セリ)。ソンジャが韓国から種を持参して農場近くの森の中を流れる小川のほとりに植えたものである。セリは日本原産で春の七草のひとつ。韓国ではキムチ、チゲ、汁物等、様々な料理や薬草に使われている。作品タイトルのミナリは、たくましく地に根を張り、二度目の旬が最もおいしいことから、子供世代の幸せのために親の世代が懸命に生きることを意味しているという。有害野生生物でないとしても外来種を無断で植える行為は問題だが、それを誰も指摘しないほど、小川のほとりのセリ畑のシーンは美しいと言える。
参考文献
※1 Korean Immigrants in the United States br> https://www.migrationpolicy.org/article/korean-immigrants-united-states-2017
※2 Asian American and Pacific Islander Heritage Month: May 2020 br> https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2020/aian.html
※3 初生雛鑑別法の発展と普及(日本家禽学会) br> https://jpn-psa.jp/video/
【ミナリ】
- 公式サイト
- https://gaga.ne.jp/minari/
- 作品基本データ
- 原題:MINARI
- 製作国:アメリカ
- 製作年:2020年
- 公開年月日:2021年3月19日
- 上映時間:116分
- 製作会社:A24、プランBエンターテインメント
- 配給:ギャガ
- カラー/サイズ:カラー/シネマ・スコープ(1:2.35)
- スタッフ
- 監督・脚本:リー・アイザック・チョン
- 製作総指揮:ブラッド・ピット、ジョシュ・バチョーブ、スティーヴン・ユァン
- 製作:デデ・ガードナー、ジェレミー・クライナー、クリスティーナ・オー
- 撮影:ラクラン・ミルン
- 美術:ヨン・オク・リー
- 音楽:エミール・モセリ
- 編集:ハリー・ユーン
- 衣装デザイン:スザンナ・ソング
- キャスティング:ジュリア・キム
- キャスト
- ジェイコブ:スティーヴン・ユァン
- モニカ:ハン・イェリ
- ソンジャ:ユン・ヨジョン
- デビッド:アラン・キム
- アン:ノエル・ケイト・チョ
- ポール:ウィル・パットン
(参考文献:KINENOTE)