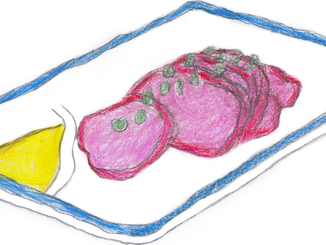グローバリゼーションの進展、インバウンドの増加などもあり、外国や外国人に対するイメージは変わりつつあり、一方、外国や外国人から見た日本や日本人のイメージも変わりつつあるように思われる。そこで思い出されるのが、「イエロー・フェイス」というものである。
かつてハリウッド映画においては、白人俳優が特殊なメークアップを施して東洋人を演じることが普通に行われていた。黒人以外が黒人を演じるときに施したメークアップを「ブラック・フェイス」と呼ぶように、非東洋人が東洋人を演じるメークアップは「イエロー・フェイス」と呼ばれる。本稿では、1910年代のサイレント時代、1930年代のモノクロ・トーキー時代、1960年代のカラー・ワイドスクリーン時代のイエロー・フェイスが登場する映画3作を振り返り、あわせて、それらで扱われた食の話題も取り上げたい。
西洋人から見た“東洋人らしさ”
本連載ではかつて「外国映画の中の“勘違い”日本食文化」というタイトルのシリーズを展開したことがあった(本連載第109回、113回、117回参照)。シリーズ中でとりあげた「東京ジョー」(1949)の早川雪洲や、「東は東」(1952)と「東京暗黒街 竹の家」(1955)のシャーリー・ヤマグチ(山口淑子)はまぎれもない本物の東洋人である。
これに対し、非東洋人が東洋人を演じるイエロー・フェイスとは、オペレッタ「ミカド」(1885年初演)やオペラ「蝶々夫人」(1904初演)といったヨーロッパの舞台で行われた、黄色いドーランを塗って目尻をこめかみ側に無理やり引っ張って吊り目に見せる東洋人メイクをハリウッド映画に持ち込んだのが始まりである。
なぜこのようなイエロー・フェイスの手法がとられたのかについては、ふたつの理由があると、「イエロー・フェイス ハリウッド映画にみるアジア人の肖像」(村上由美子著・朝日選書)は説明している。以下はその引用である。
ひとつは単純に、演技力のある東洋系俳優の絶対数が足りなかったから。もうひとつは、東洋人というのがアメリカ自身の手で「解釈」され、アメリカ社会に「翻訳」されて初めて理解される存在だったからである。東洋人自身が演じるリアリティーはこの際必要ではなかった。それはかえってアメリカの持つオリエント・ビジョンを邪魔し、混乱させるものでしかない。枠からはみ出てはせっかくの「解釈」が成り立たないのである。
つまり私たち日本人が、アメリカ映画やヨーロッパ映画で日本絡みのシーンを観て、描写がおかしいと感じたとしても、その日本の描写は西洋人自身によって解釈、翻訳された“日本らしさ”である可能性が高いということらしい。東洋人と西洋人の認識の違いを念頭に、以下紹介する三作をご覧いただければ幸いである。
※注意!! 以下はネタバレを含んでいます。
「散り行く花」のイエローマン
映画の黎明期に「国民の創生」(1915)、「イントレランス」(1916)などでモンタージュ、カットバック、クローズアップなどの映像技術を実践、映画文法の基礎を確立し「映画の父」と呼ばれたD・W・グリフィスが1919年に監督した「散り行く花」は、ハリウッドにおけるイエロー・フェイス初のヒット作である。
野蛮な西洋人に仏の教えを説こうと中国の港町からロンドンに渡ったものの、現実の壁に直面し、貧民街で阿片や博打に明け暮れている雑貨店主の中国人青年を、白人俳優のリチャード・バーセルメスが演じている。シーンやカットの合間に挿入される字幕には名前ではなく直球で「Yellow Man」と表記される始末。サブタイトルも「THE YELLOW MAN AND THE GIRL」となっている。THE GIRLにあたる薄幸の少女ルーシーは、グリフィスのミューズ(muse/芸術家にインスピレーションを与える人物)であるリリアン・ギッシュが演じている。
ルーシーはボクサーの父バロウズと二人暮らし。バロウズはルーシーが生まれてまもなくルーシーの母に逃げられている。ルーシーはバロウズから日常的に虐待を受けており、虐待から何とか逃れようと口角を指で上にあげて作り笑顔を見せ、バロウズのご機嫌をとろうとする。この仕草は本作のキーになっており、グリフィスに影響を受けたゴダールが「勝手にしやがれ」(1960)で、ジャン・ポール・ベルモンドにこれに似た仕草をやらせている。
さて、バロウズの食事はルーシーが作っているのだが、給仕の際に料理をバロウズの手にこぼしたことでバロウズから鞭による激しい虐待を受ける。この食事の際の虐待がきっかけとなり、ルーシーの家出、行き倒れたルーシーをイエローマンが助けるというストーリー展開につながっていく。イエローマンは邪心なしにルーシーを助けているのだが、ルーシーに近付く際のエキセントリックな仕草が観客の不安をあおるような演出になっている。この演出は、公開当時の一般的なアメリカ人が抱いていた東洋人像を反映しているのかも知れない。
「大地」の王龍と玉蘭
「大地」(1937)は、中国育ちのアメリカ人女流作家パール・S・バックが1931年に発表しノーベル文学賞を受賞した長編小説の映画化した作品だが、舞台は中国でありながら主役は中国系ではない俳優が演じている。貧農から紆余曲折を経て大地主に成り上がる華北の農民・
中国を舞台に、イエロー・フェイスが英語で会話する光景は、東洋人から見ると奇異に映るかも知れない。不自然さを緩和するためか、主演以外の俳優には中国系俳優も起用された。ちなみに、王龍と玉蘭の長男役を演じた中国系俳優ケイ・ルークは、後に「グレムリン」(1984)でチャイナタウンの骨董屋店主を演じた。
本作のキーアイテムは桃。王龍が大地主の屋敷を訪ね、奴隷として働いていた玉蘭を嫁としてもらい受けた帰途、王龍は桃を買い、玉蘭にも渡す。王龍は歩きながら桃を食べた後、種を道端に捨てるが、玉蘭がその種を拾う。
植えたら木になるわ
その夜、玉蘭は王龍の家の庭に桃の種を「きっと育つ」と念じながら植える。桃の種が芽を出し苗木になった頃、玉蘭は長男を妊娠。玉蘭が出産直前まで働いた甲斐あって、王龍の家は5つの畑を持つほど豊かになり、次男と長女も生まれる。
ところが突然の干ばつが華北を襲い、王龍一家は飢餓を避けるため南の都会に逃れ、乞食にまで落ちぶれる。そんな中で辛亥革命が発生。革命の混乱の中で玉蘭は宝石の入った袋を拾う。宝石を元手に帰郷した王龍一家を、満開の花をつけた桃の木が迎える。さらに畑を買い足して大地主となった王龍を祝福するように、桃の木にたくさんの桃が結実する。
実は物語はここで終わりではなく、大地主となって
「ティファニーで朝食を」のユニオシ
最後に紹介するのは、オードリー・ヘップバーン主演の「ティファニーで朝食を」(1961)。トルーマン・カポーティが1958年に発表した小説を「ピンクの豹」(1963)のブレイク・エドワーズが監督した。音楽は主題歌の「ムーン・リバー」がアカデミー歌曲賞を受賞したヘンリー・マンシーニ。
映画冒頭、「ムーン・リバー」のインストゥルメンタルが流れる中、早朝のニューヨーク・ティファニー前にジバンシィのリトルブラックドレスを身にまとったカフェ・ソサエティ・ガール(現代日本で言うところの“港区女子”的なイメージに近い)のホリー(ヘップバーン)が、イエローキャブで乗りつけ、ティファニーのウィンドウを眺めながらペイストリーをかじりコーヒーを飲むシーンはあまりにも有名である。

そのホリーのアパートの上階に住んでいるのが日本人写真家のユニオシ。演じているのは「青春一座」(1939)、「二人の青春」(1941)などの「アンディ・ハーディ・シリーズ」で主演を演じた元MGMミュージカル子役スターのミッキー・ルーニーである。ユニオシは、吊り目に、丸眼鏡に、出っ歯に、着物、という日本人ステレオタイプのイエロー・フェイスで登場する。ちなみに、日本人では聞き慣れないユニオシという名前は、「クニヨシ」など別の名前をカポーティがアレンジしたと推測されている。
ユニオシは、鍵を失くす癖があるホリーのために毎回玄関の鍵を開けねばならなかったり、階下でホリーが立てる騒音に悩まされたりと、ホリーに対する苦情が絶えないが、いつかホリーに写真のモデルになって欲しいと思っているので我慢しているようだ。作中ではユニオシの部屋の描写もあるが、丸提灯のような照明器具の下に布団を敷いて寝ていたり、豆絞りの手ぬぐいを鉢巻きにして入浴したり、抹茶を点てたりと、日本人ステレオタイプ的な描写が多い。こうした誇張した表現については批判も多いようで、監督やプロデューサーは後に反省の弁を述べている(※)。
本作に登場する食べ物のトピックは、ティファニー前のペイストリーのほかに二つある。一つ目は、ホリーが最近アパートに越してきた作家のポール(ジョージ・ペパード)とティファニーを訪れ、店員に「クラッカー・ジャック」のおまけの指輪に名前を刻んでほしいと無茶振りするシーン。「クラッカー・ジャック」とは、日本の「キャラメルコーン」(東ハト)に似た、1896年から発売されているスナック菓子である。野球のメジャーリーグの試合で7回表終了時に歌う「私を野球に連れてって」(Take Me Out to the Ball Game/Jack Norworth作詞、Albert Von Tilzer作曲)の歌詞にも“Buy me some peanuts and Cracker Jack”と「クラッカー・ジャック」の名前が登場する。ちなみにこの歌を元にした「私を野球に連れてって」(1949)というミュージカル映画も存在する。
クラッカー・ジャックにおまけが付くようになったのは1912年から。年配の店員が自分が子供の頃にもおまけが付いていたと懐かしんで名入れを承諾するという流れになっている。
もう一つは、スクランブルエッグも作れなかったホリーが、ブラジルの富豪との結婚が決まった途端に料理を始め、「チョコレートソースをかけたチキンとサフランライス」を作ろうとするが失敗してしまうシーン。チョコレートソースと言うと甘いソースを想像してしまうが、メキシコ料理ではダークチョコレートやココアを他の調味料と煮込んでビターで深みのある風味に仕上げる「モーレ・ポブラーノ」というソースがあるという。
おわりに
最近巷で外国人問題が話題になることが多い。本稿の内容とは直接関係ないが、イエロー・フェイスの映画を観てあまりいい気持ちがしないように、逆の立場になったことを考えて、自分とは異質な人たちに先入観を持つことは控えるべきだと思う。「散り行く花」でイエローマンが西洋人の水兵たちに諭したセリフをもって本稿の結びとしたい(イエローマンはブッダの教えと言っているが、実は「論語」にある孔子の言葉)。
What thou dost not want others to do to thee, do thou not to others.
(己の欲せざる所は人に施すこと勿れ)
※『ティファニーで朝食を』日本人への偏見「ユニオシ」の変化と、真田広之がたどり着いた栄冠の意義 | THE RIVER
https://theriver.jp/yunioshi-history/
- 本連載第109回
- https://www.foodwatch.jp/screenfoods0109
- 本連載第113回
- https://www.foodwatch.jp/screenfoods0113
- 本連載第117回
- https://www.foodwatch.jp/screenfoods0117
- 東京ジョー
- Amazonサイトへ→
- 東は東
- Amazonサイトへ→
- 東京暗黒街 竹の家
- Amazonサイトへ→
- イエロー・フェイス ハリウッド映画にみるアジア人の肖像
- Amazonサイトへ→
- 国民の創生
- Amazonサイトへ→
- イントレランス
- Amazonサイトへ→
- 散り行く花
- Amazonサイトへ→
- 勝手にしやがれ
- Amazonサイトへ→
- 大地
- Amazonサイトへ→
- 大地(小説)
- Amazonサイトへ→
- 科学者の道
- Amazonサイトへ→
- グレムリン
- Amazonサイトへ→
- ティファニーで朝食を
- Amazonサイトへ→
- ティファニーで朝食を(小説)
- Amazonサイトへ→
- ピンクの豹
- Amazonサイトへ→
- ムーン・リバー(サントラ)
- Amazonサイトへ→
- 青春一座
- Amazonサイトへ→
- 二人の青春
- Amazonサイトへ→
- 私を野球に連れてって
- Amazonサイトへ→
- 論語
- Amazonサイトへ→
【散り行く花】
- 作品基本データ
- 原題:Broken Blossoms
- 製作国:アメリカ
- 製作年:1919年
- 公開年月日:1922年4月2日
- 上映時間:76分
- 製作会社:ユナイテッド・アーティスツ
- 配給:ユナイテッド・アーティスツ
- カラー/サイズ:モノクロ/スタンダード(サイレント)
- スタッフ
- 監督・脚本・製作:D・W・グリフィス
- 原作:トーマス・バーグ
- 撮影:G・W・ビッツァー、K・ブラウン
- 編集:ジェームズ・スミス
- 特殊効果:ヘンドリック・サートフ
- キャスト
- ルーシー:リリアン・ギッシュ
- イエローマン:リチャード・バーセルメス
- バロウズ:ドナルド・クリスプ
(参考文献:KINENOTE)
【大地】
- 作品基本データ
- 原題:The Good Earth
- 製作国:アメリカ
- 製作年:1937年
- 公開年月日:1937年11月1日
- 上映時間:138分
- 製作会社:メトロ・ゴールドウィン・メイヤー
- 配給:MGM支社
- カラー/サイズ:モノクロ/スタンダード
- スタッフ
- 監督:シドニー・A・フランクリン
- 脚色:タルボット・ジェニングス、テス・スレシンガー、クローディン・ウェスト
- 原作:パール・バック
- 原作戯曲:オーウェン・デイヴィス、ドナルド・デイヴィス
- 撮影:カール・フロイント
- アソシエイト・プロデューサー:アルバート・リュイン
- キャスト
- 王龍:ポール・ムニ
- 玉蘭:ルイゼ・ライナー
- 王龍の父:チャーリー・グレイプウィン
- 長男:ケイ・ルーク
- 次男:ローランド・ルイ
- 蓮華:ティリー・ロッシュ
- 叔母:ソー・ヨング
- 叔父:ウォルター・コノリー
- 従兄弟:ハロルド・ヒューバー
- 劉(穀物商人):オラフ・ヒッテン
(参考文献:KINENOTE)
【ティファニーで朝食を】
- 作品基本データ
- 原題:Breakfast at Tiffany’s
- 製作国:アメリカ
- 製作年:`1961年
- 公開年月日:1961年11月4日
- 上映時間:115分
- 製作会社:パラマウント映画
- 配給:パラマウント映画
- カラー/サイズ:カラー/アメリカンビスタ(1:1.85)
- スタッフ
- 監督:ブレイク・エドワーズ
- 脚色:ジョージ・アクセルロッド
- 原作:トルーマン・カポーティ
- 製作:マーティン・ジュロー、リチャード・シェファード
- 撮影:フランツ・プラナー
- 音楽:ヘンリー・マンシーニ
- 編集:ハワード・スミス
- キャスト
- ホリー:オードリー・ヘップバーン
- ポール:ジョージ・ペパード
- 2E:パトリシア・ニール
- ドク・ゴライトリー:バディー・エブセン
- ホセ・ダ・シルヴァ・ペレイラ:ホセ・ルイ・ド・ビラロンガ
- メグ・ワイルドウッド:ドロシー・ウィットニー
- ユニオシ:ミッキー・ルーニー
(参考文献:KINENOTE)