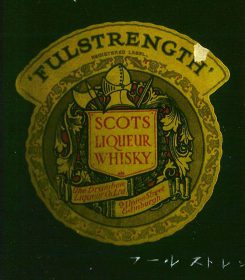日本に洋酒文化が定着していったプロセスを読み解く第2シリーズ。ゾルゲが飲んでいたと思われる3銘柄が浮上したが、このうちの一つは「なぜ?」と思わせるところがある。また、いま一つは、どのようなものであったかが全くわからない。
戦前の「ネプラス・ウルトラ」とは
「ネプラス・ウルトラ」(Ne plus ultra)は「デュワーズ・ホワイトラベル」(Dewar’s White Label)の上級品(12年物)で、80年代まで普通に流通していたおかげで日本のバーでも認知度は高いが、保存状態で品質にブレがあるのか、筆者は唸るほどの名品に会ったことがない。
何より、25年熟成のモルトウイスキー「レア・オールド」や、“カスク”(樽出し/無加水)である「フルストレングス」(FULSTRENGTH)と比較して、12年物の「ネプラス・ウルトラ」(Ne plus ultra)では味の好みはともかくスペック上では格下感が否めず、長谷川がプレミアムに推す理由は以前から謎だった。そもそも日本に根強いファンが多い「ピンチ」(Pinch=ディンプル/Dimple)も12年物であり、ネプラスの下に置く必然性が見当たらない。
だが、ここで戦前のバーのメニューにあった「ネプラス・ウルトラ」と、現在プレミアのブレンデッド・ウイスキーとして六本木辺りで名高いデュワーズ社の「ネプラス・ウルトラ」が別物である可能性を付記しておきたい。実はNe plus ultraは「至高」を意味するフランス語から来ており、そもそもデュワーズ社が独占する名称ではない。今日ネットでもほとんど見掛けないが、1950年代以前にシェリー樽で20年熟成した、全く別の「ネプラス・ウルトラ」がHepburn社というところから出ていた時期があり、長谷川が“超”が付く他の高級ウイスキーと並べたのはこちらかもしれないのだ。
ブキャナン社のトップブランドだった「レア・オールド」
「レア・オールド」はRARE OLD LIQUEURと当時のラベルに表記されている。現在のたいていの英和辞典はliqueurを“酒に果実や甘味などを加えたもの”としており、今から40年ほど前に日本で出版された洋酒辞典でも同様の説明がなされている。だが、かつてLiqueurはプレミア・ウイスキーのラベルにもElixir(精髄)に近い意味で使われており、むしろ高級品の証とされていた。
肝心の中身は、現在も二匹の犬のマークで有名な「ブラック&ホワイト」の製造元であるブキャナン社の25年物で、当時の価格(1927年創業の「ボルドー」で2円と、およそ「ネプラス・ウルトラ」の倍)にもそれが反映されている。明治屋酒類事典によれば、英国国王ジョージ5世から大正天皇に元帥杖が贈られたことを記念してブキャナン社が大正10(1921)年に発売したという。

ブキャナンのプレミアム・ブランドとしては、多くのバーテンダーの方が、昭和天皇が皇太子時代に訪英した縁で英国と日本限定で販売が許された「ロイヤル・ハウスホールド」(Royal Household)を思い浮かべるはずだが、当時の「サロン春」のメニューでは「レア・オールド」が1円30銭、「ロイヤル・ハウスホールド」が90銭だったし、昭和9(1934)年の卸売相場表でも前者が170円(1ダース)に対して後者は120円(同)だったから、「レア・オールド」が明治40(1907)年から皇室御用達の栄を受けていたブキャナン社のトップブランドだったことがわかる。
筆者は10年近く前に「レア・オールド」を調べた原稿を「男の隠れ家」に執筆したことがある。その際、昭和5(1930)年に実際に使われていた「レア・オールド」のラベル写真を含む複数の写真を入手していたのだが、白黒写真の悲しさで、この瓶の封印として両肩に貼られていたリボンの色がどうしてもわからない。その際もイラストをお願いしていた藤原カムイ氏と二人で色をどうすべきかモノクロ写真の資料を前に散々話した結果、彼は「この瓶やラベルの配色、そしてモノクロ写真の色調から見て、この色以外にあり得ない」と断じてリボンを紫に近い赤で描いた。
後に同誌を見た親切な読者がカラー写真を送ってくれてこの色が正解であることが分かり、藤原氏の慧眼に敬服すると共に胸をなでおろしたことも、今では思い出となっている。
「フルストレングス」はカフェーで1杯1万円超
長谷川が下した評価は高くないのだが「フルストレングス」は最高級品に挙げていい。「ボルドー」のメニューには掲載されていないものの、本稿を書く上でたびたび使わせていただいている「銀座社交料飲協会八十年史」掲載の「クロネコ」と「サロン春」のメニューでは、他を差し置いて断トツの値段でリストに並んでいる。
ウイスキーを樽に貯蔵している間の目減り分を「天使の分け前」と優雅な表現を使うが、天使に気前よく分け前を振る舞っていれば樽の中身が目減りするのも道理で、その結果加水せずに出荷するカスクとなるとどうしても割高になる。
文人が愛した「サロン春」でこれを一杯頼むと1円50銭で「バット69」(80銭)の倍近く取られた。庶民が10銭バーで模造品を飲んでいた時代である。筆者がよく使う「庶民の味方、カレーライス・レート」で見ると、浅草の大衆食堂でカレーが10銭(昭和8年)だったから、これを500円に換算して現在だと一杯7500円というところだろうか。当時のカフェーでは「1円はチップをはずまないとカフェー遊びはできない」と言われていたから、一杯飲むのに軽く1万円を超えることになる。

筆者がまだ現在ほど資料を持っておらず、ネットの普及など別世界の話だった10年以上前に昭和2年創業の「ボルドー」のメニュー、それも実物を店内で見せていただいたときのことはいまだに覚えている。現在では筆者の中で当たり前になっている、戦前のバーが何種類もスコッチやカクテルをそろえていたことさえ当時の自分には驚きだった。
その店で「ホワイトホース」や「ジョニ黒」を差し置いて一番高額だったのが「カメオ」ブランドで、それに次ぐ高級ウイスキーが「レア・オールド」だった。今から10年近く前に書いた原稿を読み返してみると、まだ手探り状態で幻のウイスキーの記憶があるバーテンダーを探して銀座を彷徨していた自分の姿が見える気がする。
「カメオ」は謎に包まれたブランドで、いっとき某洋酒輸入代理店でグリーンラベルの8年物が入っていたのだが、いくらなんでも8年物をプレミアとして長谷川が推すはずがない。このブランドが戦前の日本のバーでは後述の「レア・オールド」とともに高級ウイスキーの代名詞だったようで、現在でも営業している昭和2年創業の銀座「ボルドー」の他に「クロネコ」のメニューにも掲載されていた。
最大の極秘情報打電の夜
1941年。ゾルゲとブーケリッチが、寝静まった東京の街で周囲の物音に神経を尖らせて警戒するのを横目に見ながら、クラウゼンが無線機を組み立て、日本海を隔てた1000㎞以上向こうの国境に向けてモールス信号を打ち始める。
「こちら、ラムゼイ(ゾルゲの暗号名)。ヴィースバーデン局(擬装用にドイツの地方名を冠したウラジオストックの無線基地。ゾルゲと同志たちは最後までそれがどこにあるのかを知らなかった)応答願います」
ややあってクラウゼンのレシーバーに応答がある。
「……こちら、ヴィースバーデン。受信感度は良好。ラムゼイ、発信を開始せよ」
発信位置を特定されないようアタッシェケースで搬送可能にした小型無線機はコンデンサーやトランスがむき出しで、触れると感電する危険な代物だった。見えない相手が息を呑んで待ち受ける、日本海の遙か彼方に強力な電波を届けるため、定格の倍の電圧をかけた送信器の真空管は送信から20分もすると高電圧に悲鳴を上げ始める。
猛烈なスピードでキーを打ち終えたクラウゼンが送信を終了して耳のレシーバーを置いたとき、緊張が解けて3人で酌み交わしたウイスキーは、したたかに心にも染みたに違いない。
(画・藤原カムイ)