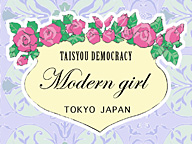日本に洋酒文化が定着していったプロセスを追う本シリーズ。その手がかりとして最初にスポットを当てたのが、大正期から現れたモダン・ガールたちだ。その中に、現在一般にイメージされるのとはちょっと違うモダン・ガールがいた。名前を尾竹紅吉という。好奇心旺盛な彼女がひき起こしたある事件が、当時の洋酒事情への興味をかき立てる。
話題の店に現れた青鞜の女
明治44年女権運動ののろしを上げた雑誌「青鞜」は、後に伝えられる名声とは裏腹に創刊当初は発行が1000部、最盛期でも3000部を超えることはなかった。
それがどの程度の規模だったかを当時の資料で比較すると、明治42年に「婦人世界」が40万部、これを追って創刊された同文舘の「婦女界」でさえ創刊号は5万部という記録がある。今はネットで「青鞜」を検索すると5万件以上がヒットするが、「青鞜」が発刊した明治44年の段階では、出版の規模から言えば同人雑誌レベルだったということになる。
1部25銭の売り上げでは印刷代もままならず、「青鞜」は常に本体の売上げ以外の収入、有体に言えば広告を取る必要に迫られていたのだが、そのことが日本の洋酒の歴史に思わぬ影響を与えることとなる。
明治45年6月のある日。日本橋小網町に人力車がようやく行き来するだけの幅に架けられた小さな橋の名を鎧橋という。そのたもとに前年開店したばかりのフランス料理店「メイゾン鴻之巣」に、大柄でがっちりした浅黒の女性がやってきた。男物の久留米絣の着物にスフの袴、角帯といういでたちである。彼女は店の主人である奥田駒蔵に、去年創刊された女性雑誌に広告を出してもらえないかと用件を切り出した。聞けば発行部数は1000部というから広告の効果には甚だ疑問があるのだが、後に自ら文芸雑誌を創刊するほど文学好きの奥田は熱心に雑誌「青鞜」の理念を説く彼女の言葉に動かされる。
色は浅黒で丸顔。鼻筋も通っているわけではない。およそ美人とはかけ離れた顔なのだが、その話しぶりは天真・素朴で正直そう。「邪気が無い」という表現そのままの彼女の熱い語り口に根負けする形で、奥田は広告の依頼を受けることにした。
5色に注ぎ分けたプース・カフェ
……神戸大学大学院の中山修一教授の手になる「表現文化研究」第8巻2号「富本憲吉と一枝の家族の政治学(2)」に示されたこの女性に関する考察と、同書が資料として挙げた大正元年の「萬朝報」「國民新聞」から奥田駒蔵と尾竹紅吉(本名:一枝)の出会いを復元すると、このような感じだったらしい。
(以下、尾竹に関する記述は主に同書と「青鞜の女・尾竹紅吉伝」に依っている。また、彼女の容貌に関するいささか手厳しい記述は筆者の想像ではなく、大正2年、実際に尾竹にインタビューした雑誌「新潮」記者が書いた彼女の印象を基本的に引用している)

当時、東京では帝国ホテルの他にも「精養軒」「東洋軒」「中央亭」等でフランス料理を出していたが、帝国はイブニングかモーニング着用が必須で、不意に来た普段着の客には紋付き袴を貸して着させていた時代であり、気軽に本格フレンチを出す奥田の「メイゾン鴻之巣」が目を引いていた。
この店を立ち上げた奥田駒蔵は、文学の世界で有名なパンの会と「カフェー・プランタン」、戦前の名バーテンダー濱田晶吾がシェーカーを振る「カフェー・ライオン」へとつながるカフェー文化の流れを作った功労者でもある。本稿では、駐ベルギー大使館の料理人を務めた彼が璃球兒杯(当時の文学者木下杢太郎は「リケエルグラス」と表記している)で尾竹の前に差し出したのが「プース・カフェ」と呼ばれる、グラスの中で5色に分かれたカクテルだったことがポイントとなる。
尾竹は、さっそく「青鞜」の明治45(大正元)年7月号に「其美少年(尾竹の自称)は「鴻之巣」で五色のお酒を飲んで今夜もまた(らいてう)氏の圓窓(自宅)を訪れたとか」と書いている。
リキュールを集めた尾竹紅吉
これが、その後メディアから「所謂(いわゆる)新しい女」として彼女たちがバッシングを受ける「五色の酒事件」なのだが、その後の騒動については上掲書やネットに任せて、本稿は洋酒に特化したアプローチをかけていく。
お酒のことなど何も知らない、好奇心旺盛な19歳の娘の前で、欧米帰りの店主が手品のように5色に注ぎ分けたカクテルを差し出した……こう書くとドラマチックでもあるし、筆者も当初はこういった情景を頭に思い描いていた。「五色の酒事件」について書かれた文献も、多くはこのスタンスに従って書かれている。
ところが、彼女は広告を取りに行く前から、当時は珍しかった洋酒、わけてもリキュールに関する知識をどこからか得ていたことを示す興味深い事実が、上掲した中山教授の引用資料から出てきた。尾竹が「メイゾン鴻之巣」を訪れる前月の明治45年5月、彼女が自宅に「青鞜」同人を招いた際の招待状を引用する。
「桃色のお酒の陰に、やるせない春の追憶を浮べて(中略)私たちの仕事に異大な祝福の祈りを捧げ乍ら靑いお酒を汲み合ひたいと思ふ。(中略)紅吉は、黄色い日本のお酒とそして麥酒と洋酒の一、二種とすばしこやのサイダを抜いて待って居る」
この文章は「……紅吉は、その日、その夜の來るのを子供の様に數へて待って居る。さよなら」で終わっている。創刊時から「青鞜」編集部に熱烈なラブレターを送り続けたことが平塚らいてうに認められ、とうとう念願かなって「青鞜」の同人に加えられた彼女。その招待状の文章の端々に、晴れて「青鞜」の一員となった嬉しさが滲んでいる。彼女の天真爛漫さについつい本題を忘れそうになるが、ここは心を鬼にして、次回は文中に出てくる酒に注目しよう。
(画・藤原カムイ)